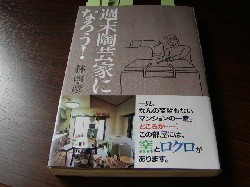|
陶芸仲間からのおすすめ本 |
| ブック名 | 週末陶芸家になろう! |
著者 |
林寧彦 |
| 発行元 | 双葉社 | 価格 | 1680円(ユースド1400円) |
| チャプタ | 「はじめに」僕のマンション工房へようこそ ①窯 ②焼成 ③ロクロ ④唐津焼き ⑤CMプランナー ⑥酒器と食器 ⑦白化粧 ⑧釉薬 ⑨ノート ⑩道具 ⑪インターネット ⑫公募展 ⑬帰任 ⑭週末陶芸家の週末 ⑮陶芸工房・漂流記 |
キーワード | やりたいこと、道具、白化粧土、釉薬、好きなこと、半乾燥、素焼、文様、自分のもの(イメージ) |
| 本の帯(またはカバー裏) | 一見、なんの変哲もないマンションの一室。 ところが・・・!この部屋には窯とロクロがあります。 |
気になるワード ・フレーズ | ・僕は、一計を案じた。職住接近で、しかも1人暮らしなら自分の時間がたっぷりできる。 その時間を徹底的に陶芸に使ってやろう。考えようによっては、単身赴任は憧れの工房を 手に入れるチャンスなのだ。 ・(電動)ロクロまわりで気をつかったのは、水こぼれしたときの対策と壁紙を汚さない工夫、 それに階下の人への配慮である。床全体は工事用のビニールシートですでに覆ってある。 水を使うロクロまわりは、用心のためにさらにビニールカーペットを敷いた。 ・次に壁紙を汚さないよう、トベの飛び散りそうな範囲をビニールで覆った。 胸の高さまであれば十分。ビニールはテーブルカバー用のもので、薄手のもので、 ピンで壁にとめた。 ・ひたすら湯飲みだけを作った。もういちど基本をやり直そうと思った。手順を体に覚えさせる ことときちんとした形を作ることに徹した。作っては削り、作っては削りを繰り返し。 ・「いいコピーが書けるかどうかは、どんな少年時代を過してきたかだよ」なにをきれいと感じ、 なにに感動し、なにに涙を流したか・・・。 ・「自分でドキドキしながら、この器作った?」 ・吉野さんの工房に向かう山道は、いつも思いがけない愉しみを用意してくれる。 ・素焼きしてから白化粧を施したほうが安全なのだが、僕は半乾燥の状態で掛ける。 「生掛け」といわれるやりかただ。素焼きよりも水分の吸収が少ないから土とのなじみがよく、 焼き上がったときに白の濃淡が微妙に出て情趣があって好きだ。 ・調合してテストを繰り返していると自分がどんな色で調子を求めているのか分からなく なってしまうことがある。・・・求める「黒」のイメージが自分ではっきり見えていないと、 いくらテストを繰り返してみても単なる実験マニアの化学少年である。・・・答えは釉薬の 調合の中に見つかるのではなく、自分の体の中にあるのではないか。 ・食器の縁のあたりにこんな文様を描き入れればプロっぽいぞ。そんな色気も働いた。 ・「手にできないことが、その先に道具を付けてできるわけがない。 |
| かってに感想 | 陶芸教室に通って4年目である。 技術的な進歩に少し悩んでいる。 というのは、電動ろくろをやってみたいが、マンションではどうかなあと・・・・・。 そこで、ジオシティーズの「ホビー・陶芸」にホームページを登録している仲間から、 情報はもらえないかと探してみた。 なんとマンションに電動ロクロを入れ、外に物置を置き、窯まで設置している方が いらっしゃったのだ、それも女性の方なのである。 もちろん初めての方なのだが、図々しくもメールを送信したら、 いろいろとアドバイスもしてくれて、この本まで紹介してくださったのである。 早速、アマゾンで本を検索し買い求めた。 もちろん中古本なのだ。 4日に注文し、翌日の5日には到着。 その日に読み始める まずは、この本の「はじめに」を読んで、「やってみる」勇気を与えられる。 それはこんなフレーズである。 「なにかを始めるとき、できない理由は山のようにあるものだ。できる理由はただひとつ 『それでもやりたいから』」なのだ。 本題をへ入っていくといきなり驚かされる。 なぜか、それは150kg?もする窯がマンションに搬入されていくからなのだ。 マンションの中に「窯」ウソ!!ホントなのである。 ずっと読み進めると、作者は4年間陶芸教室に通い、転勤・単身赴任を機会にマンション 工房を始められた方のようだ。 なんと行動的な方か、この本の中には、自分で窯を持って 自分で釉薬を作って、陶器に自分で自由に絵を描いて、焼いてみたい人にとっては、いろいろな ノウハウが満載である。 その一方で、自分は陶芸をするに当たって、何に凝ってみたいのか、 色、形、それとも・・・自分のイメージができあがっていないと、 かなり相当苦しい道のりであることをアドバイスしてくれるのだ。 さて、窯のことはまだ先の話として、 私にとっては電動ろくろ選びのことが書かれていないことが残念だった。 でも、いろいろ参考になることがあり、特に3つほど早速やってみたいと思った。 まずは、成形の基本技術を繰り返してマスターすること。 2つめは、白化粧土を塗布して、素焼きし、そのキャンパスに絵を描いてみること。 そして、3つめは模様を残してまわりの化粧を落として素地を出す「かき落とし」を やってみること。 その他にも、「象嵌」「ノート付け」「文様」「白化粧土に蚊帳の布目」等々・・・。 おわりになってわかったことがある。 題名は「週末陶芸家になろう」だが、たゆまない陶芸のための下準備の継続 が下地にある。 決して、筆者は週末陶芸家ではない、ただ単に陶芸で金儲けをしない完全なプロの陶芸家 なのだと確信した。 |
| キッチン陶芸 | 一筆がき俳画の描き方 | 蛙 かえる カエル |