仕上げ・高台作り  |
*乾燥具合を確認する。 *乾燥が十分でない場合、ドライヤーを利用して全体を乾かす。 *口を付けるところを水平に整えるか、でこぼこのままにするかは適当にし、 水平に整える場合は、低いところよりもう少し低目に合せる。 *底の部分が1cm以上あれば、高台作りをする。 *高台は、口径の2分の1より大きくし3分の2程度とする。 *ろくろにぐい呑みを逆さにして中心部に置き、脇を固めて円を作るツール使用して ろくろを回転させ、二重の円を描く。 *底の部分・横の部分の厚さを確認しながら、ツールで削る。 (注)・要は、安定した高台と、平均的な厚さに整えるため削る。 ・高台のしきりははっきりとつける。 ・底に近い部分が厚くなりがちなので、厚さを確かめながら削る。 ・削った粘土は、はけを利用してはらう。 *底の部分が1cm以内であれば、ぐい呑みの場合、底の外側部分は へこます程度にする。 *縁部分や高台は尖らせないで削る。 *底の裏面に自分のサインマークを鉛筆で入れる。 |
日本手ぬぐいの使い方と成形後の作品の持ち方   |
*日本手ぬぐいは、人差し指と中指で上部を、薬指と親指で引っ張る。 *指と指の間のところをならしたい個所にあてて、調整する。 *作品の移動は、両手の人差し指と中指の間で挟んで持つ。 |
柄の取り付け  |
*コーヒーカップの柄・・・付け位置寸法約2倍弱にする。 *形は自由に考えて端は切る。少し太目にし、中へ押し込むようにして曲げていく *持つことが目的であり、全体とのバランスを考えて形作る。 *カップへの取り付け位置を定める。 *カップ、柄相互に溶かした粘土を付けて、擦り付けるようにカップに柄をつける。 *柄を取り付け後は、カップは逆さにしておく。 *半日〜1日は、ボックスに入れる。 |
面取り
|
*器の側面を曲面としないで平面としたもの。 *この側面を削る時は、カツターナイフを利用して大胆に削る。 |
小皿削りとシッタ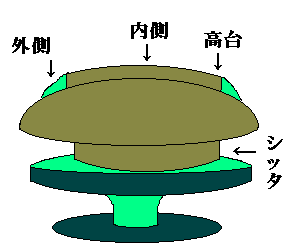 高台際の厚み 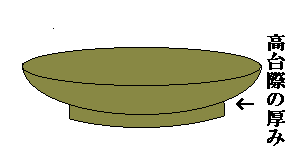
|
<小皿削り> *底の厚さの確認・・・高台口径3分の2。 *先に外側削り。 *内側削り・・・高台の高さ、見た目のバランスが大切であるが、 高台際(重みの負担がここに集中するため)の厚みがそれ以上に大切。 (注)薄いと高台から外側部分がしなる。 *シッタの高さは、皿の深さ・大きさにあわせて。(安定感を見ながら) (注)シッタ(けずり台)は粘土でろくろの中心部に作り、適当に乾燥させる。 *ろくろの回転を利用して大胆に削る。 *適当に削り、厚さをみながら、また削る。 <皿の乾燥> *口縁の一方的な乾きを防ぐため、ビニール・新聞などをかけ、 日蔭で時間をかけて乾燥(とくに大皿)。 |
|
<<袋物(徳利)>> <肩作り> <首作り> <口の作り> <胴の丸み>  |
*底は大きめ、広げすぎない。 *積み上げまっすぐしぼる。 *ひもは細めに、つなぎ目は丁寧に。(粘土の3分の1を残し、ひも状にして使用) (注)表面が光るだけになるので、あまり水をつけすぎないこと。 *厚みはそろえて広げすぎない様に *底の厚みは、1cm、確実にとる。 *内側の底は適当なところでならす。(出来上がった時には修正できない) |
<袋物削り>
 |
<シッタの作り方> *口の小さなもの・・・皿。 *口縁が水平でないものの、削り、仕上げ工程で使用。 *口縁は太めて゜なめらか、胴は締め、やや広げる。 *植木鉢などを使用してもよい。 *口縁は徳利の肩の大きさに合わせ外に開く。 <高台削り> *底・腰の厚みを事前によく頭に入れておく。 *全体のバランスを見ながら |